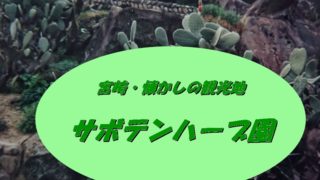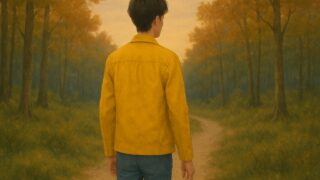地震や津波などの自然災害に対する備えが重要視される今、宮崎市でも地域の安全を守るための対策が進められています。特に南海トラフ地震のリスクが指摘されている中で、避難タワーの整備や活用は市民の命を守るための鍵となります。
この記事では、宮崎市の避難タワーの概要からその場所、利用方法、整備状況、そして地域住民との関わり方まで、わかりやすくご紹介します。
宮崎市の避難タワーとは

宮崎市の避難タワーの目的
避難タワーは、津波や高潮といった自然災害時に、安全な高所へ迅速に避難できるよう設けられた施設です。
特に海岸沿いや標高の低い地域では高台が少なく、迅速な避難が困難なため、避難タワーは非常に重要な役割を果たします。宮崎市では住民が迷わず避難できるよう、各施設に案内表示や避難誘導サインを整備しています。
また、これらの施設はバリアフリー対応や広さ、安全性を考慮して設計されており、高齢者や子どもも安心して利用できるよう工夫が施されています。避難訓練や住民説明会なども定期的に実施されており、避難タワーの存在を地域に浸透させる努力が続いています。
南海トラフ地震に対する備え
南海トラフ地震は、広範囲に深刻な被害をもたらすとされる巨大地震であり、宮崎市も津波被害のリスクが高い地域に含まれています。そのため、垂直避難を前提とした避難タワーの整備は喫緊の課題となっています。
宮崎市では、避難にかかる時間をシミュレーションし、地形や人口密度を考慮して最適なタワーの配置を進めています。加えて、避難路の安全確保や視認性の高い誘導標識の整備、避難所マップの更新など、多面的な取り組みが強化されています。
避難タワーの利活用を地域住民に広めるため、防災イベントや自治会主催の避難訓練も積極的に行われています。これにより、災害時に慌てず冷静な判断と行動ができるよう、日常から意識づけを行うことが目的です。
避難タワーの指定施設について
宮崎市では、津波避難に対応するための指定施設として、学校や病院、商業ビルなどの耐震構造を持つ建物を登録しています。これらの施設は、災害時に高齢者や子どもを含む誰もが安全に利用できるように整備されており、各地域に配布されている防災マップでもその位置が明記されています。
さらに、避難タワーに加えて、公園内にある展望台や多目的スペースも避難施設として整備されており、身近な場所で避難できる環境が拡充されています。また、昼夜を問わず出入りできるよう、鍵の開放管理や夜間照明の設置も進んでいます。
加えて、民間施設の協力も年々進展しており、スーパーやホテル、商業ビルなど、日常的に多くの人が集まる施設が避難場所として機能できるよう登録が広がっています。災害時の受け入れ体制が強化されることで、地域全体の安全性向上につながっています。
避難タワーの場所
宮崎市内の主要避難タワー
青島・木花地区など津波被害が想定される地域に重点的に設置されています。特に以下の施設は、地域住民の安全を確保するために設置された重要な避難拠点です。
- 青島中学校(青島西2丁目)
- 木花小学校(学園木花台北)
- 加江田地区避難ビル(加江田木花台付近)
また、佐土原町の「二ツ立避難タワー」(佐土原町下田島15165-1)や、宮崎空港旅客ターミナルビル(赤江無番地)なども避難施設として指定されています。これらの施設は、地域ごとの防災計画に基づいて整備され、住民への案内や誘導体制の整備も進められています。
さらに、ホテルや老人ホームなども避難先として登録が進んでおり、例えば「ホテルAZ宮崎佐土原店(松小路7-8)」や「介護老人保健施設ことぶき苑(本郷北方4043-1)」も緊急避難場所に含まれています。
宮崎市海岸沿い地域の避難場所情報
海岸沿いには複数の避難ビルや防災ステーションが整備されています。特に赤江地区やその付近の地域には、以下のような高層建築物が避難施設として指定されています。
- セントヒルズマリーナ宮崎壱番館・弐番館(赤江1247)
- ソフトタウン高洲(高洲町235-3)
加えて、赤江大橋周辺や新別府川沿い、新別府町の一部など、津波の到達が早いとされる地域には、地域密着型の避難ステーションや高台避難所(城ヶ崎や熊野エリアの一部)も整備されています。
これにより、海岸近くに住む住民も短時間で安全な場所へ避難できる体制が整いつつあり、今後も整備の拡充が予定されています。
参考:宮崎市緊急避難場所
避難タワーの利用法

津波避難の流れと手順
地震発生直後は、高台または避難タワーへの速やかな移動が基本です。特に沿岸地域では、地震発生から数分以内に津波が到達する可能性が高いため、ためらわず直ちに行動を開始することが求められます。
普段から、自宅や職場から最寄りの避難タワーまでの最短ルートや複数の避難経路を確認し、実際に歩いてみることが効果的です。所要時間を把握しておけば、緊急時にも落ち着いて行動できる可能性が高まります。
また、夜間や大雨・台風時などの悪天候を想定した準備も重要です。懐中電灯、防水靴、レインコートなどを防災袋に入れておくと安心です。定期的に家族で避難シミュレーションを行うことで、いざというときに迷わず行動できます。
地震発生時の避難行動
強い揺れを感じた場合、最初にすべきは身の安全を確保することです。屋内にいるときは、倒れやすい家具やガラス製品から離れ、机の下に身を隠して頭を守るなど、安全な姿勢を取るようにしましょう。
揺れが収まった後は、建物の損傷や落下物に注意しながら屋外に出て、できるだけ早く津波の影響が予想される地域から離れます。津波警報や注意報が発令された際は、テレビやラジオ、スマートフォンの公式防災アプリなどで最新情報を必ず確認しましょう。
近くに避難タワーがない場合には、周囲の高台や避難指定建物に向かうことが推奨されます。地域によっては標識や案内板が設置されているため、普段から場所を把握しておくことが重要です。
一時避難所利用時の注意点
一時避難所は災害時に多くの人が集まる場所となるため、混雑や物資の不足などが想定されます。避難の際は、事前に避難タワーや指定避難所の位置とルートを家族や周囲の人と共有しておくと安心です。
また、持ち出し袋には飲料水、非常食、モバイルバッテリー、衛生用品、簡易トイレなど、最低限の生活用品を入れておきましょう。特に高齢者や小さなお子さんがいる家庭では、常備薬やおむつなども忘れずに準備してください。
避難所では共同生活が前提となるため、他の避難者と協力し合う姿勢が求められます。避難所のルールを守り、思いやりのある行動を心がけることで、安心・安全な環境づくりに貢献できます。
避難タワーの整備状況

新たに整備された避難ビル
2024年以降も宮崎市では津波や地震対策として新しい避難ビルの整備が積極的に進められており、地域全体のカバー率の向上が図られています。特に、これまで避難施設が不足していた沿岸部や人口密集地域に重点的に整備されており、より多くの住民が短時間で安全な場所へ避難できるよう配慮されています。
具体的には、赤江・青島エリアの高台や、交通アクセスが良好な主要幹線道路沿いに、複合機能を備えた新型避難ビルが建設され、災害時だけでなく日常の地域活動にも利用されるよう設計されています。屋上スペースにはヘリポートや備蓄倉庫、太陽光発電設備を備えるなど、持続可能な災害対応施設としての機能も強化されています。
既存タワーの対応状況
既存の避難タワーについても順次改修が進められており、耐震補強やバリアフリー化、避難ルートの見直しなどが実施されています。夜間の視認性を高めるLED照明の設置や、多言語対応の案内看板の追加など、利用者にとってより安全でわかりやすい施設づくりが進行中です。
また、地域住民との連携を強めるため、施設の一部は地域交流スペースとしても開放されており、平時から親しみのある場所として活用されています。
今後の計画と整備想定地域
今後は特に高齢者福祉施設周辺や観光客が多く訪れる青島・堀切峠・日南海岸エリアなどにおいて、新たな避難施設の整備が予定されています。災害弱者とされる方々の迅速な避難を支援する目的で、介護施設や集合住宅の隣接地にタワー型避難施設を設置する計画も進められています。
加えて、公共交通機関との連携を図るため、バス停や駅周辺における避難案内や緊急時の誘導体制も強化されており、観光シーズン中でも安心して行動できる環境が整えられつつあります。
地域住民への影響
住民の避難意識向上について
定期的な訓練や広報活動によって、宮崎市内の住民の防災意識は年々高まっており、避難行動への関心や理解も深まっています。市が発行する防災ハンドブックや、地域の掲示板、学校の広報誌などを通じて、避難タワーの活用方法や避難ルートの案内が積極的に伝えられています。
また、自治体主催の講習会や、自治会・町内会が実施する勉強会では、過去の災害事例を交えた解説や、具体的な避難行動のシミュレーションが取り入れられており、住民の防災意識を高める大きな役割を果たしています。近年では、若年層への啓発にも力が入れられ、小中学校での防災授業やワークショップも定期的に開催されています。
避難タワーと地域の防災対策
地域ぐるみで避難タワーを活用した防災活動が行われており、各自治体や町内会と連携して、災害発生時の行動手順を共通理解とする取り組みが進んでいます。特に、避難タワー周辺の住民には年に数回の避難訓練参加が奨励されており、その際にタワーの構造確認や避難所での受付体験なども実施されています。
地域によっては、防災リーダー制度を導入し、災害時の情報伝達や高齢者の誘導を担うボランティア体制が構築されつつあります。このような仕組みは、緊急時における混乱の防止や迅速な対応を可能にする基盤となっています。
地域イベントと避難訓練
防災イベントや学校での避難訓練は年々活発に実施されており、多くの住民が自主的に参加しています。例えば、市内各地では「防災フェスタ」「地域防災の日」などの催しが行われ、避難所での炊き出し訓練や応急処置の体験、地震体験車の利用など、実践的な内容が多く取り入れられています。
さらに、学校では児童・生徒が家庭に持ち帰る防災プリントや、親子で参加できる避難訓練も実施されており、家庭単位での防災意識向上にもつながっています。こうした地域イベントと訓練は、防災に対する理解を深めるとともに、住民同士のつながりや助け合いの精神を育む大切な場にもなっています。
防災情報の発信

避難情報の受信方法
防災無線、スマホアプリ、緊急速報メール、テレビ・ラジオ放送など、宮崎市では複数の手段を通じて避難情報を受信することができます。特に、「宮崎市防災アプリ」では、地域ごとの避難情報や災害発生状況をリアルタイムで受信できるようになっており、通知機能をオンにすることで、深夜や屋外にいるときでも情報を確実に受け取ることが可能です。
また、災害用伝言板や市のSNS(XやFacebookなど)でも随時情報が発信されており、複数のルートから情報を得ることが重要です。家族間での情報共有をスムーズにするためにも、利用するツールを事前に決めておくと安心です。
宮崎市の防災マップの活用法
宮崎市の防災マップは、市の公式ウェブサイトにて最新版がダウンロード可能です。地域ごとの避難場所、津波浸水想定区域、避難ルートなどが色分けされてわかりやすく掲載されており、災害時に迅速かつ安全に行動するための有効なツールとなっています。
※なお防災マップは以下のリンクから確認できます。
宮崎市防災マップ(公式) および 国土交通省ハザードマップポータルサイト もあわせて参照すると、全国的なリスク情報も把握できます。
紙媒体のマップも市役所や地域の公民館、図書館などで配布されており、インターネットを使用しない方や高齢者にも配慮された体制が整えられています。
また、2023年4月より提供が開始された宮崎市公式の防災アプリ「Hazardon(ハザードン)」では、スマートフォンで避難場所の表示や災害情報の受信が可能です。プッシュ通知機能により、リアルタイムで避難情報を取得することができます。
■詳細はこちら:宮崎市 防災アプリ「Hazardon」について(公式サイト)
マップには最寄りの避難タワー、公共施設、福祉避難所の情報も明記されており、自宅からの距離や所要時間を事前にシミュレーションすることで、最適な避難行動を計画することが可能です。家族全員で防災マップを見ながら、避難ルートを定期的に確認しておくことが非常に大切です。
定期的な情報更新とその重要性
防災に関する情報は、季節や社会情勢によって変化するため、常に最新の内容を確認することが重要です。宮崎市では、年に数回のペースで防災関連情報を見直し、ウェブサイトや広報誌などで更新内容を発信しています。
また、災害対策基本法の改正や防災指針の見直しに伴い、避難に関する基準やルールも変化する場合があります。定期的に情報を確認することで、災害時にも混乱せず落ち着いて行動することができ、家族や地域の安全確保にもつながります。
避難タワーの事例紹介
今は普段は鍵がかかっている津波避難タワー、いざという時スムーズに使えるよう、どうすればいいのか。今回の事態を受けて市も対応を検討するそうです。
津波避難タワー、住民が一時入れず混乱 宮崎・日向灘の地震時:朝日新聞デジタル https://t.co/PVmoikJghB
— 朝日新聞宮崎総局 (@asahi_miyazaki) August 22, 2024
宮崎市の避難タワーの特長
宮崎市の避難タワーは、地域密着型である点が大きな特徴です。公共施設や民間施設を併用した設計となっており、日常的に地域住民が利用している建物を避難場所として登録することで、いざというときに迷わず避難しやすい環境が整えられています。
また、地形や人口密度、避難時間などを考慮し、各地域に最適な構造が採用されているのも特徴です。例えば、複数の出入口を持つ設計や、屋上に備蓄倉庫や非常用電源を設置するなど、災害時に機能する「拠点」としての役割が重視されています。
他自治体の取り組みと比較
高知県や和歌山県などの太平洋沿岸部では、宮崎市と同様に津波被害を想定した避難タワーの整備が進められており、情報共有や技術交流も行われています。たとえば、高知県では一部地域において津波避難タワーに通信機能や防災無線設備を備えるなど、情報発信拠点としての機能を持たせています。
和歌山県では観光地である白浜地区に観光客向けの避難案内を多言語化し、地域外からの来訪者にも配慮した設計が特徴です。宮崎市でも、今後は観光地である青島・日南海岸周辺での整備と情報表示の多言語対応が計画されています。
避難タワーへの要望と改善点
避難タワーについては、地域住民からの声を反映し、バリアフリー化や設備の拡充が求められています。特に高齢者や身体の不自由な方々の利用を想定し、エレベーターの設置や手すり、滑り止め床材の導入などの改善要望が多く挙がっています。
また、タワー周辺の照明や案内板の設置、備蓄物資の保管体制なども課題とされており、市では順次改善に向けた計画を進めています。災害時だけでなく、平時にも活用されることで防災意識の向上にもつながる設計が今後の課題です。
地域コミュニティと避難タワーとの絆
避難タワーは単なる避難施設としてだけでなく、地域コミュニティを支える場としての役割も果たしています。防災訓練や地域イベントの拠点としても活用され、住民同士の交流や協力体制の強化につながっています。
たとえば、地域の子どもたちが避難タワーを使って体験学習を行うなど、世代を超えた学びと関わりの場になっており、防災意識を自然と育む教育効果も期待されています。こうした取り組みを通じて、避難タワーが地域全体の連帯感を高める象徴的な存在となっているのです。
まとめ
宮崎市の避難タワーは、地震や津波といった自然災害に対する備えとして極めて重要な社会インフラのひとつです。海岸沿いを中心とした地域では、高台への避難が難しい地理的条件を抱えているため、避難タワーの存在は、住民の命を守るために欠かせない存在となっています。
特に近年は、避難タワーの数が増加し、機能の強化も進んでいることから、防災意識の向上とあわせて、地域全体の安全性がより確保されつつあります。日頃から、ハザードマップの確認や避難ルートの見直し、家族との連絡手段の共有といった備えを整えておくことが、緊急時に冷静な判断と迅速な行動へとつながります。
また、定期的に行われている防災訓練への参加や、地域コミュニティでの情報共有を通じて、住民同士の協力体制を築いておくことも重要です。防災は日々の積み重ねが何よりも力になります。災害時に自分と大切な人の命を守るためには、普段から正しい知識と心構えを持って行動することが、最も効果的な備えとなるでしょう。