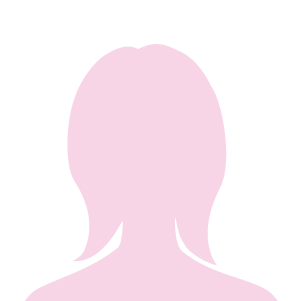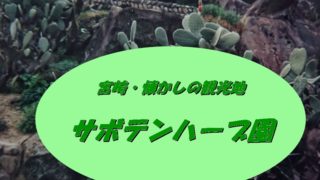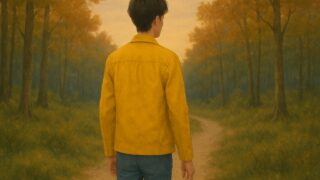「MRTのAMラジオが休止」と聞いて、驚いた方も多いのではないでしょうか。
しかし、この動きは単なる地方局の一例ではなく、日本全国のラジオ放送が大きな転換期を迎えている証でもあります。
この記事では、MRTのAM送信所休止の背景をはじめ、総務省の制度的な枠組み、NHKや民放局の今後、そして「AMラジオは本当に消えるのか?」という疑問への答えまで、幅広く解説します。
これからのラジオのあり方を、前向きに知っておきたい方へ。
記事を通じて、時代に合わせて変わりゆくラジオ放送の「今」と「これから」を掴んでいただけたら嬉しいです。
- MRTがAMラジオの送信を一部休止する本当の理由とは?
- 総務省が進める「AM局運用休止の特例措置」の中身
- NHKと他の民放AM局がどんな方針を打ち出しているか
- AMラジオ終了後の代替手段と、ラジオの未来像
MRTのamラジオ休止はなぜ?背景や理由を詳しく解説
#mrtラジオ#んダモシタン西諸Radio
今日も14時からの放送です今回のゲストは
MRTラジオ局
局長の「春口さん」です今年12月1日から
都城・小林(西諸エリア)・日南の3つの中継局からのAM電波でのラジオ放送を休止するお話や
AMからワイドFMに切り替えるお話
ラジコのお話など語って下さいます❣️ pic.twitter.com/wUArNxQFG7— 大野勇太 (@ono_yuta) October 11, 2025
2025年12月、宮崎のローカルラジオ局 MRT(宮崎放送) の一部AM送信所が運用を休止するという発表がありました。このニュースを目にして、「ラジオって、もう終わっちゃうの?」「なぜ今?」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
まずは「MRTがAM放送をなぜ休止するのか?」という疑問にフォーカスして、制度的背景や地域への影響、そして今後のラジオの行方についても掘り下げて解説していきます。
MRTのAM放送が終わる?いつ・どう決まったの?
まず最初に押さえておきたいのは、「いつからAM放送が休止されるのか」という点です。
MRTは公式に、2025年12月1日から、以下の3つのAM送信所を休止すると発表しました:
- 都城中継局
- 小林中継局
- 日南中継局
この動きは、総務省が設けた「AM局運用休止の特例措置」を活用して進められたものです。つまり、これは単なる経営判断ではなく、国の制度的な後押しを受けて進められているということになります。
ポイントは、「休止=完全終了ではない」という点。
一時的に運用を止めて、その影響や代替手段の有効性を検証する「実証的取り組み」として行われるもので、将来的なFM転換やAM廃止に向けた第一歩とも言える内容です。
なぜ休止に?経営や技術の問題が背景に
では、なぜMRTはAM放送の運用をやめる(止める)という判断に至ったのでしょうか?
そこには、現代の放送を取り巻く複合的な問題が関係しています。
主な理由は以下のとおりです:
- 送信設備の老朽化:交換や維持に莫大なコストがかかる
- 電力コストの増大:AM送信所は非常に電力を消費する
- 聴取者の減少:若年層を中心にAMを利用する人が激減
- 代替技術の普及:FM補完放送(ワイドFM)やradikoが浸透
特に地方局にとっては、「聴いてくれる人が少ない中継局」を高いコストで維持し続けるのは、ビジネスとして成り立たないという厳しい現実があります。
また、技術的な面でも「FM波の方が音質が良く、今の時代に合っている」という点も見逃せません。MRTではすでにワイドFM(93.4MHzなど)での放送もスタートしており、AMの役割は徐々に終わりに近づいているとも言えそうです。
地域の人への影響はある?
もちろん、放送が休止される地域に住んでいる方にとっては、直接的な影響も出てきます。
特に懸念されるのが:
- 高齢者層で 「AMラジオしか聞いたことがない」 人
- FMが届きづらい山間部などの 電波難視地域
- 災害時の緊急情報が AMでしか受信できない 状況
MRT側では、「ワイドFMやradikoで聞けますよ」という案内をしており、FMチューナーやスマホを使った聴取方法を紹介しています。ただ、全ての人がすぐに対応できるとは限らず、情報格差への対策やサポートも求められるでしょう。
中には、「なぜ地元のラジオが聞けなくなるのか?」という不安や不満の声もあがっており、地域への丁寧な説明と周知がカギとなります。
総務省によるAM局運用休止の特例措置とは
MRTがAM送信所を一部休止する背景には、総務省が設けた制度的なサポートが存在します。それが、「AM局の運用休止に係る特例措置」と呼ばれる制度です。
この特例措置は、ラジオ業界全体にとっても大きな転換点と言える制度ですので、ここではその内容や目的、MRTとの関係性を詳しく見ていきましょう。
特例措置の概要と目的(総務省の方針)
この制度は、簡単に言うと、「AM放送を一時的に休止してもいいですよ」という国からのお墨付きを与えるものです。
背景にあるのは、次のようなラジオ業界の実情です:
- AM送信設備の老朽化とメンテナンス負担の増加
- 人口減少と聴取者の変化によるリスナーの減少
- 災害時以外でのAMの利用頻度の低下
こうした課題に対し、総務省は「いきなりAMを全部やめるのではなく、まずは一部を止めて実験的に影響を見てみましょう」という方向性を出したのです。
この制度には段階的な導入期間が設定されており、放送局は「第一期」「第二期」などに分けて申請することが可能です。
つまり、MRTが中継局を休止するという動きは、この特例措置に基づいた正式な制度の中で行われているということです。
適用期間と対象局一覧にMRTは入っているのか
この制度は2021年からスタートし、既に全国各地のAM局が申請・運用休止を進めています。
たとえば:
- 第一期:2023年11月~2025年1月
- 第二期:2025年9月~2026年10月
この期間内に、14社以上の放送局が休止申請を行っており、全国的に「AMを止めてみる」局が増えています。
MRTもその一社であり、都城・小林・日南の中継局は、制度に沿った正規の手続きを経て休止することが分かっています。
特に地方の中継局は、リスナー数に対して維持コストが高く、この制度を活用して検証・整理する動きが進んでいるのです。
今後のAMラジオのあり方と制度的な流れ
この制度は単なる「一時休止」で終わるものではなく、将来的なAMのあり方を決めるためのプロセスでもあります。
今後想定されるステップは、次のような流れです:
- まずは一部の中継局を運用休止
- 実際の聴取影響や代替手段の有効性を検証
- リスナーや地域の意見、実績をもとに廃止・存続を判断
さらに、総務省は将来的にFM転換や完全撤退も選択肢として制度設計を進める方針を示しています。
そのため、今私たちが目にしているのは「AM放送終了」ではなく、次の時代への移行に向けた“準備段階”といえるのです。
この点を理解しておくと、MRTのAM中継局休止というニュースも「衝撃的な終了」ではなく、未来への一歩としての決断であることが見えてくるはずです。
NHKと他の民放AM局はどうなる?
MRTのAMラジオ休止は、地方局のひとつの決断ですが、実はこの動き、日本全国のAM放送局で共通の課題となっています。
中でも注目されるのが、NHKの対応と、他の民放AM局の動向です。
ここでは、2025年10月時点で明らかになっている最新の情報をもとに、それぞれの立場と未来への方向性を見ていきましょう。
NHKはAM放送をどうする?
NHKは、2026年度からラジオ第1とラジオ第2を統合する方針を発表しています。これにより、現在の3波体制(ラジオ第1・第2・FM)を2波体制へと再編し、放送の効率化を図る計画です。
ただし注意したいのは、「AM放送をすべて廃止するわけではない」という点です。
NHKは公共放送として、全国民に放送を届ける法的義務(放送法)を負っており、全地域でAMをゼロにするには法改正が必要になるほどです。
また、災害時の情報伝達手段としてもAM波は重視されており、一気に廃止するような方向性は現時点で否定されています。
つまり、NHKは段階的・慎重な再編を模索している状態であり、「AMとFMの適正なバランス」を取りながらサービスを維持する姿勢を示しています。
他の民放AM局では休止・転換の動きが加速中
一方で、民放AM局はより現実的な問題に直面しています。地方局を中心に、運用コスト・設備老朽化・収益減といった課題から、「AMからの撤退」を進める動きが急速に広がっているのです。
2025年現在、すでに:
- 13社34中継局以上がAM送信所の運用休止を発表
- 第二期特例措置(2025年9月~2026年10月)に14社が申請
- CBCラジオや東海ラジオなどが長期休止の局を公開
このように、民放AM局は「維持が困難な中継局から順次整理していく」ことで、段階的なFM移行・インターネット移行を模索しています。
ワイドFM(FM補完放送)やradikoなどの活用が進む中で、AMを使わないリスナー層が拡大していることも、こうした流れを後押ししているのです。
今後の見通し:FMとネットに主軸が移る時代へ
この流れを総合して考えると、今後のラジオ放送は、AM → FM+インターネットという構造へと確実にシフトしていくことが予想されます。特に民放局にとっては、聴取者数の減少とコストの上昇というダブルパンチを受けている中、デジタル移行・波の集約は避けられない選択肢となってきています。
ただし、全国一斉でのAM廃止はまだ現実的ではなく、地域ごとの事情を加味しながらの段階的対応が求められているのが実情です。これからのラジオは、FM・ワイドFM・インターネット・アプリ・スマートスピーカーなど、複数のプラットフォームで共存する“ハイブリッド型”になっていくでしょう。
その中で、私たちリスナーも、「どこでどう聴くか?」という選択肢を柔軟に持つことが求められる時代に入ってきたのかもしれません。
AMラジオはなくなるのか、残るのか?──結論と今後の見通し
MRTのAM中継局運用休止や、各局の動向を見て「このままいくと、AMラジオは本当に消えてしまうのでは…?」と感じた方も多いのではないでしょうか。
ここでは、「AMラジオは完全に消えるのか、それとも一部残るのか?」という点を、現時点で分かっている最新情報をもとに詳しくお伝えします。
完全消滅ではないが、縮小は避けられない
まず結論から言えば、「今すぐAMラジオが全国一斉に無くなる」ということはありません。しかし、将来的に“必要な部分だけが残る”という方向には確実に進んでいます。
その理由は大きく3つあります:
- NHKは2026年度にラジオ第1・第2を統合予定としつつも、AM波そのものの廃止は明言していない
- 放送法上、NHKには全国民への放送提供義務があるため、AM全廃には法改正というハードルがある
- 災害時や山間部など、FM・インターネットが届きづらい地域では、AMが今も重要なライフラインとなっている
つまり、公共放送の性質や、防災インフラとしての側面を踏まえると、一定数のAM放送は今後も必要とされる可能性が高いのです。
民放各局は「脱AM」へ向けて動き出している
一方で、民放AM局はより現実的な判断を迫られています。収益の厳しさ、送信所の維持費、リスナーの減少など、AMを維持する意味が薄れている局が増えているのが現実です。
- 2028年秋までにFM転換・AM廃止を目指す局も複数存在
- 総務省も「特例措置後のAM廃止選択可」という制度設計を進行中
- 都市部を中心にradikoやFM補完放送へシフトする聴取習慣が定着
つまり、民放に関しては「段階的なAM撤退」が既定路線になりつつあると言えます。
ただし、全局・全地域で同時にAMを廃止するのではなく、リスナーの状況や代替手段の整備状況を見ながら進めていくのが基本方針です。
残るAMの役割:災害情報と地方インフラ
今後、AMラジオが完全に消えることはないとしても、その役割は大きく変わっていくでしょう。
その中で残される役割とは、次の2点に集約されます:
- 災害時の非常通信手段としての活用(電波の届く距離が広く、停電にも比較的強い)
- インターネットやFM波が届きにくい地域の“最後の放送手段”
たとえば、地震や台風でインターネット回線が寸断されたとき、最後に頼れるのはAMラジオというケースもあります。また、山間部や離島では、FMの受信状況が安定せず、AMが唯一のメディアであることも少なくありません。
このような背景から、完全なAM撤退には慎重な姿勢が求められているのです。
AMは縮小しながら“しぶとく生き残る”可能性が高い
いま私たちが見ているAMラジオの姿は、変化の真っただ中にあると言えます。
- 大都市圏ではradiko・FMが主流
- 地方局は設備の縮小と再編
- 一部中継局は撤退しつつも、AM全体は消えていない
このように、今後のAMラジオは、「一部が撤退し、必要なところだけが残る」というバランス型の形に落ち着いていくでしょう。
つまり、AMラジオは“消える”のではなく、“変化して生き残る”。
それが現時点での最も現実的な見通しです。
MRT休止後のラジオ放送の今後と代替手段
MRTの一部AM送信所の運用が休止されたあと、ラジオはもう聴けないの?と思う方もいるかもしれません。
でも、ご安心を。
MRTをはじめ、多くの放送局ではAMの代わりとなる新しい聴取手段がすでに整備されており、これまで以上に便利に楽しめる方法も増えてきています。ここでは、MRTのAM終了後に利用できる代替手段や、今後のラジオの楽しみ方について解説します。
ワイドFMとは?MRTは対応済みか
ワイドFM(FM補完放送)とは、AM放送の弱点(ノイズ、音質、地形による影響など)を補うために設けられた、FM波によるAM番組の再送信です。
MRTではすでに93.4MHzの周波数でFM補完放送を実施しており、都城・小林・日南でAMが休止されたあとも、FMラジオを使えば引き続き番組を聴くことが可能です。
ワイドFMは:
- 音質が良く、雑音が少ない
- 一般的なFMラジオ(90~95MHz対応)で受信可能
- 屋内や高層建物でも比較的安定した受信が可能
AMからワイドFMに移行するだけでも、聴きやすさはグッと向上するはずです。

インターネットラジオやアプリでの聴取環境
もうひとつの大きな選択肢が、インターネットを使ったラジオ聴取です。
代表的なのが radiko(ラジコ)。これは全国のラジオ局が参加する公式サービスで、スマホ・PC・タブレットなど、どんなデバイスからでもラジオ番組を楽しむことができます。
radikoの魅力は:
- 宮崎だけでなく全国のラジオ局が聴ける
- 「タイムフリー機能」で過去1週間の番組を聴き直せる
- 「エリアフリー(有料)で全国の放送を聴取可能」
また、MRT公式アプリや、スマートスピーカー(Amazon Alexa・Google Home)でも声で再生操作が可能になりつつあり、デジタル時代に合ったラジオの聴き方がどんどん広がっています。
地域密着メディアとしてのラジオの価値は変わるか
たとえ放送手段が変わっても、ラジオの「地域の声を届ける」価値は変わりません。
MRTをはじめとするローカル局は、地元のニュース、交通情報、防災情報、イベント情報など、生活に密着した情報源として地域に根付いています。特に高齢者や地元住民にとって、「顔なじみのアナウンサーの声」や「なじみの番組」は、日々の安心や癒しにもつながっているのです。
さらに、災害時にはネットが遮断されても、FMやスマホの非常電源でラジオを聴ける環境は、防災対策の一環としても重要視されています。
今後は、以下のような“多チャンネル対応型のラジオ”が一般化していくと予想されます:
- FM補完放送
- インターネット配信(radiko・アプリ)
- スマートスピーカー連携
- 音声コンテンツとの融合(Podcastなど)
つまり、ラジオは“古いメディア”ではなく、時代に合わせて進化している「現役の情報メディア」と言えるでしょう。
まとめ
- MRTは2025年12月から都城・小林・日南のAM送信所を運用休止予定
- 休止は総務省の「AM局運用休止の特例措置」に基づくもの
- この制度は段階的なAM放送の縮小・検証を目的としている
- NHKは2026年度からラジオ第1と第2を統合予定(AM完全廃止ではない)
- 民放AM局では34局以上が中継局の運用休止を実施または計画中
- 将来的にAMラジオは一部地域を除いて縮小・整理される方向にある
- AM廃止後の代替手段としてFM補完放送(ワイドFM)が進んでいる
- radikoやスマホアプリなど、ネットラジオの利用者も増加中
- 災害時の情報伝達手段として、AMは一部で存続の可能性あり
- ラジオは“古いメディア”ではなく、進化しながら残っていく存在
AMラジオの休止という話題は、一見すると寂しいニュースに思えるかもしれません。しかし実際には、放送の形を時代に合わせて変えていこうという前向きな動きです。FM、インターネット、アプリなど、選択肢は広がっており、ラジオの魅力はこれからも残り続けます。
これを機に、自分に合った新しい聴き方を見つけて、これからもラジオを楽しんでいきましょう。